
日本テーラワーダ仏教協会の機関紙『パティパダー』に連載中の巻頭法話をご紹介します。スマナサーラ長老が、日常生活のなかで出会う問題に即して仏教の教えを説かれた人気コーナーです。ダウンロードして、ごゆっくりお読みください。
協会事務局では、長老の説法ビデオテープやカセットテープ、書籍などを、多数用意し販売しております。無料で差上げる本もありますので、ぜひご連絡ください
(1) 敵を作らない人間の真の生きかた
人間はこの世に生まれ落ちたときから、“競争社会”の一員としてスタートさせられる運命にあります。小学校や中学校で猛勉強させられていい大学に入るのも、人よりいい人生を歩むためという大義名分の元で人に負ける… (2) 罰の罰
<人に係わっていくための約束事>
罰という概念は人間だれでも好むものではありません。「私は罰せられることが好きですから、いつでもどうぞご遠慮なく罰をあたえてください」というひとはどこを探し…
(3) 心の逃走
<人はなぜ苦しみ悩むのか>
私たちは、この世に生を受けてからというもの常に悩みごとに見舞われています。物ごころのついたそれこそ子供のころからお小遣いが少ないとか、もっとおもちゃが… (4) 悪魔に勝つために <1>
<自分は美しい人間か>
元来人間の精神は脆弱であると言いきっても差し支えないとおもいます。「もっと良い人間になりたい」「自分というものを高次に磨いていきたい」「崇高な目的に…
(5) 悪魔に勝つために <2>
<自由闊達な心を求めて>
人間の身体を清浄なものと思いこむことは、即ち悪魔(煩悩)につけ入る間隙を与える愚劣なる思考であるということは前号で解説したところですが、今回は人間の… (6) 真実の見つけ方
<頭だけでは何も掴めない>
釈迦尊と同時代である宗教の開祖ともなったSan~jayaという有名な宗教家がいました。 釈迦尊より年が上で弟子たちも多くを数えていたようです。 仏教で一般的に言う…
(7) 心のワクチン
<苦しみ、悩みという病気に患らないために>
人類は、その歴史が始まって以来、二つの大きな悩みとともにその人間史をかたちづくってきたと言っていいのではないでしょうか。 二つの悩み、それは肉体の病い… (8)思考についての考察
<悩む人間、悩みのない人間>
人間が他の生きものに比して決定的に差があると思っていることは“考える”ということだと人間自らが認めようとしています。 動物も考えてはいると思うのですが、人…
(9)知識欲
<知って役に立つこと、知ってはいけないこと>
人間の最も尊ぶ財産とはいったい何でしょう? これこそが人間にとっていちばん欲しがるものというのはどんなものでしょう? お金でしょうか、名誉でしょうか、それとも… (10)いまの瞬間
<思い出が心を汚し、空想が心を乱す>
今回は仏教のなかでも特に重大な意味を持つといわれている appamâdaという言葉について考えてみたいと思います。この言葉はこれまでいろいろな解釈がなされて…
(11)いまの瞬間の生き方を実現する方法
<確実な解脱への道>
先月号でお話した“いま、ここ”に生きるという概念について、今月号ではもう少し掘り下げて具体的にそれを考えてみたいと思います。“いま、ここ”を実感するための実践… (12)こころはわがままです
<冥想による自己コントロール>
こころというものはなかなか理解しがたいものですが、人間が真理の道を追求するためにはどうしても理解しておかなければならない命題です。「こころ」とは何ですかと…
(13)敵と味方の見分け方
<自分のこころを育てるために>
人が生きるためには自分の敵と味方の区別をまず知ることです。結果として自分の人生を不幸にするものは敵となるでしょうし、幸福な生き方を手助けしてくれるものは… (14)すべてを勝ち抜くためには
<自分の存在証明を得る方法>
今月は「すべてに勝つ」というテーマです。すべてに勝つということを、世界征服という意味に捉らえても構いません。マンガなどでは世界征服の野望を持った主人公を…
(15)身体と幻
<執着から離れ平安な心を得る>
我々の身体は、とても大事なものです。よほど非常識な人間でない限り、「そんな事はない」などとは言わないでしょう。生まれた時から、この大事な身体を育て守るため… (16)他人ばかり観たがる心
<客観的判断と主観的判断>
人間がものごとを、自分中心に主観的に考えるというのは、その個人の固定観念に基づいたものです。ですからいつでも正しく判断できるわけではありません。ある人が…
(17)人生の目的 PART-1
<生きることは本番のないリハーサルか>
我々は生まれたときから死ぬまで、いつも必死で生きています。小さいときは勉強したりスポーツしたり、頭と体を鍛えるために忙しく過します。それは大人になってから… (18)人生の目的 PART-2
<一切の束縛から逃れる為に>
道徳的な生き方により人格を完成することを人生の生きる目的としましょうと先月号で述べました。道徳的な面で気づきながら生きることもなかなか大変なことです。…
(19)「愚か者」とは誰のことか
原始経典を読むと、「愚か者」という言葉がたびたびでてきます。たとえ出家者であっても過ちを犯すことがあります。その過ちを戒めるとき、釈迦尊は決まって「愚か者… (20)「いい影響・悪い影響」
愚か者といえば、特別に知識のない人ではなく、真理を体験しようとしないごく普通の人々のことを意味するという話を先月講義しました。そうなると次には、釈迦尊に愚か…
(21)「悩み、苦しみ」を諦められるか
仏教の立場からいえば、人間の苦しみ、悩みは人間が勝手に作っているものではないかといえます。しかし悩んだり心配したりしている人にとってはその悩みごとは… (22)賢者への道
愚か者と賢者という言葉は、今までの話のなかでたびたび出てきました。…愚か者というのは、特別に知識のない人を指すのではなく、我々のごく自然な在り方です。…
(23)「愚か者」もいろいろ
本来無知なる性格の人間が、人生を無知のままで終えてしまうようなことにならないためにはどうすればよいのかということを考察してみましょう。無知な人は結構頑固です。自分が物事を知っていると思っています。… (24)無知から生まれるわざわい
愚か者、無知な人という言葉はよく使いますが、この言葉のなかには非難する気持ちも否定する気持ちもまったくありません。「無知、愚か者」(ba^la)という言葉は我々生命が本来持っている性格を表わす仏教の専門用語です。
(25)人格と性格は変えられる
人間にとって、どんな環境で育てられ、どんな環境で生きているかということは非常に重要な問題です。それは人間の人生そのものをかたちづくり形成するものだからです。生まれてから死ぬまで、人は生きている環境から… (26)賢者人間入門 [1]
<要は心の発展にある>
仏教における愚か者という言葉の意味はこれまでにも何度も説明いたしました。愚か者にならない方法も説明してきました。今月は賢者という言葉の意味を考えてみま…
(27)賢者人間入門[2]
<感情に支配されず感情を支配する>
人間は感情に支配されています。好き、嫌い、欲望、夢、怒り、憎しみ、嫉妬、倣慢、プライド、メンツ、失望、苦しみ、悩みなどはすべて感情と言うことができるでしょう。… (28)賢者人間入門[3]
<喜びとは、真理を知ることである>
賢者という性質は持って生まれるものではありません。智慧のある人間になるためにはそれなりの努力が必要です。それなのに普通の人間は、運命、業、定め、生まれ…
(29)賢者人間入門[4]
<ネガティブ人間からポジティブ人間へ>
賢者というのは、単に智慧があるというだけではなくて、ちゃんとした人格をも持っています。すばらしい人格を形成していくことは難しいことです。人格を形成していく上に… (30)聖者(阿羅漢)の心 【1】
<すべての束縛の繋ぎから逃れ出るために>
心に何か悩みがあったり、不安があったりすると私たちは、ヴィパッサナー冥想でもしたら明るくなれるのではないかと思います。あるいは体が病気で悩まされている…
(31)聖者(阿羅漢)の心 【2】
<真の自由人間への道 >
解脱を目的として実践を続けると、心は確実に清らかな方向へ変わって行くことが感じられます。その道の終点として解脱があるのです。しかし言葉に引っばられると余計… (32)聖者(阿羅漢)の心 【3】
<たまったゴミは捨てましょう>
人はものを集めることがたまらなく好きです。人生というのはものを集めることだとも言えるほどです。生活にどうしても必要なものを集めてためておくことは、理解でき…
(33)聖者(阿羅漢)の心 【4】
<落ちつけ、落ちつけ…>
人というのは、ずいぶん忙しいものです。時計という偉大な神様に完全に管理されています。しかしもしもこの神様に言われるとおり、1秒も悩む暇なく生きていると… (34)実る生き方・1
<最後まであきらめない>
…タンパダーティカという王様の死刑執行人がいて、50年間この仕事を続けていました。あまりにも年をとってしまって、最後の頃には人を処刑するカがなくなり、刀で…
(35)実る生き方・2
<明日では遅すぎる>
ある商人達のグループが、船で商売に出かける途中に遭難しました。そのなかの商人のひとりバーヒヤは板切れにつかまってスッパーラカという島に漂着しました。… (36)本気でチャレンジ
<されど競争相手は作るな>
インドのラージャガハ(王舎城)という町にクンララケーシーという娘さんがいました。両親は大金持ちで、その娘を一歩も外へ出さないほど、大変大事に箱入りに育て…
(37)競争での勝利は勝利にあらず
<必要に迫られても悪は正当化できません>
お釈迦様はいつも、人間が幸福になる道だけを教えてこられました。全ては苦しみであるということが普遍的な真理であると教えられ、この苦しみをどのようにすれば… (38)「祈り」は宗教とは無関係
<幸福を願うなら聖者に道を学びなさい>
宗教には、儀式、儀礼などがつきものです。文明といっしょに、宗教という概念も生まれ発達してきましたが、文明の初期時代の宗教というのは、何らかの儀式を行うこと…
(39)「祈り」より正しい人間関係
<和を守る行動も仏教の道徳です>
宗教と祈りの関係をさらに考察してみましょう。宗教といえば、人の心にまず浮かぶものは、何か超自然的な対象を信じることです。その超自然的な対象に対して、祈る… (40)死ぬのは怖い?
<生きるだけが能じやない>
ある比丘のグループがお釈迦様から瞑想指導をうけて、森の中に修行に入ることになりました。釈迦尊は、行く前にサーリプッタ尊者に挨拶してから修行に…
(41)怖がるものは武器を持つ
<空虚な勇気より、自信がない方が健全>
傍若無人で身勝手で、怖いもの知らずの暴れ者は一見気が強そうに見えますが、実は根性なしで間抜けな気の弱い性格です。大概の人は、気が強くて自信たっぷり…
(42)落ち込むのは人間の本性
<良い目的はやる気を持続させる>
人の実行力、あるいはやる気というものは、あまり長く続くものではありません。すぐにやる気が消えてしまうという経験は、誰にでもあると思います。努力して、心に力を…
(43)生きることは爆弾遊びか
<無常を知るものは人生を知る>
人間を悩ませる苦しみについて、極限的な話をします。釈迦尊の時代、インドにパターチャーラーという名の大富豪の娘がいました。彼女は、召使いの間でも特に身分の… (44)悪は、心の趣味です
<勇者のみ善を行う >
「悪いことなんかはやりたくない」「いいことだけをして一生、生きていきたい」。誰に聞いても皆、このように考えているようです。それが本当であるならば、人間というの…
(45)心は癖で行動する
<心に良い習慣をつけないと自由になれません>
自由に生きているのだ、自由に考えているのだ、私は自由だ、と多くの人が思っています。自由というのは人間が好きな言葉です。自由がないと、悩んだり文句を言… (46)目先の楽しみ、は後の落とし穴
<人類の本質は過ちを犯すこと>
人はよく過ちを犯します。過ちを犯さない人間は世の中にいないのですから、過ちを犯すことが人間の特色だということもできます。人間は必ずまちがいを起こすのだと…
(47)ギネス記録症候群
<小さな善行為がすべての始まり>
「あなたは日本一だ。いや世界一だ。」と言われる人になれば、なんと幸せでしょう。でも皆自信が無く、そういう風になろうと本気になってがんばる人は、あまり… (48)危険を抱きしめるべからず
<幸福はこころ次第>
今、とても寒いですね。出かけるときには暖かい服を着て、必要ならカイロも入れて用意しないと、風邪を引くかも知れません。私なら大丈夫と高をくくる前に気をつけた方…
(49)悪に対する抵抗力
<智慧さえあればこの世の中で生きることは楽>
悪がはびこるこの世の中で、心を清浄に保つことは可能でしょうか。この地球に生きている人間社会を見渡すかぎり、賄賂、搾取、弱肉強食、不正、差別、不公平…
(50)敗者の道
<怒りの制御は幸福をもたらす>
怒りっぱなしの人生はいやだなあと、思わない人はいないでしょう。明るく楽しく、みんなと仲良く生きることができればなんて幸せなのでしょう。それはすべての人間の…
(51)無関係なことにも巻き込まれる
<危険から身を守れるのは理性のみ>
舎衛城(Sa^vatthi サーワッティ)という都市に、宝石細工職人の夫婦が暮らしていました。この夫婦は仏教を信仰し、お布施として一人の阿羅漢(聖者)の生活のお世話…
(52)心からは逃げられません
<悪事は隠し通せないものです>
悪事、不正などを行う人は、それらが露見しないようにいろいろと工夫します。しかしうまく隠し通したと安心できるのはつかの間です。悪事は必ず露見します。その不幸…
(53)なぜ殺してはいけないのか
<人類の歴史は流血の歴史です>
暴力を振るってはいけない、人を殺してはいけないというと、誰でも当たり前のことだと思うでしょう。なぜ殺してはいけないのか、なぜ暴力を振るってはいけないのかと… (54)続・なぜ殺してはいけないのか
<殺意は無知から生まれる>
自分は殺されたくはない、という気持ちは、すべての生命が持っています。「私」を理解すれば、この論理は、簡単に理解できます。「私は殺されたくない」「幸福に、楽に…
(55)言葉は核燃料か
<感情混じりの言葉は核廃棄物です>
人間の言葉は、核燃料だと思ってください。核燃料だといえば、いちいち説明しなくてもおわかりになるだろうと思います。現在、我々が必要としている膨大なエネルギー… (56)目的に向って一心にチャレンジ?
<失望しても、幸福は確保できる>
お釈迦様の信者さんにヴィサーカー夫人という裕福な女性がいました。小さい頃から家族が敬虔な仏教徒でしたので、彼女はお釈迦様の説法を聞いて、若いうちに、…
(57)悩みは自分の行いから
<人は知らず知らず悪い行いをする>
なぜ私の人生はうまくいかないのでしょう。なぜいつも何かトラブルが起こるのでしょう。あんなに気をつけていたのに、なぜ自分は病気になったのでしょう。精一杯… (58)人は苦しみの原因に固執する
<社会に幸福はあり得るか>
社会一般に見られる苦しみについて考えてみます。今の社会は昔より大変すばらしいと考えている人々がいます。「いいえ、今より昔の方がずっとよかった」と言う人々も…
(59)どこまで他人に頼りますか
<心が清らかにならない行は修行にはなりません>
人は何か困ったことがあるとき、すぐ他人に頼りたくなります。普通の人生では、いろいろなことで他人に頼らないと生活は成り立ちません。ですから他人に頼ることは、悪… (60)身なりで心が読める
<身なりを重視して中身を忘れてはならない>
身なりを整えることはとても大切だという考え方があります。見た目がいい加減であるならば、その人のことをあまり大切に思いたくないものです。社会のことを考慮。…
(61)快楽におぼれると
<仏弟子は気品高く生きるべき>
世俗的な快楽というものは、人の心を強くとらえるものです。たいていの人々は、快楽におぼれて生活しています。楽しむのはかまわないのですが、快楽におぼれると… (62)工夫の達人たち
<心は放っておけば堕落する>
Sariputta(サーリプッタ) 尊者は『智慧第一』という仏弟子達の最高の位を授けられた、お釈迦様の一番弟子でした。『智慧第一』ということは天才的な能力を持っていたと…
(63)人は幸福に盲目です
<一般人の幸福論は差別的です>
人生を楽しみたい、楽しく生きていきたい、と人は誰でも思っているのではないでしょうか。わざと苦しんで生きる必要はないのですから、人生を楽しむべきものと考え… (64)お洒落にかける人生
<身体は裏切りもの>
フェラガモ、ジバンシー、シャネルなどブランド服の’S’サイズが着られるほどのスタイルならうれしい。ナオミ・キャンベルさんみたいに細くて足が長ければ、最高…。しかし…
(65)楽のみを追うと苦を得る
<死を迎えたとき、自由な心で>
容姿について過剰に気にする必要はありません。美しくなるために神経を削ってがんばっても、美というのは個の主観であること、また、自分が「美」だと思うものも他人に… (66)悟ったつもりは危険
<刺激に対する反応でこころの状態がわかる>
お釈迦さまの時代、欲におぼれた世俗的な生き方を厭い、清浄な心を育て解脱を体験したいと思って、あるグループが皆で出家しました。出家の目的を達成するために…
(67)説法は耳障り
<美も醜も同一のものです>
仏陀の教えがたとえわかりやすくて真理であっても、みんなに親しまれたわけではありません。違う信仰を持つ人に好まれないのは当然のことですから、それは問題に… (68)文化遺産と心の遺産
<「値札」と「価値」が悪を呼ぶ>
エジプトのビラミッド、ギリシアのアポロ神段、奈良の法隆寺、日光東照宮、カンボジアのアンコールワット、インドネシアのボロブドゥール、イタリアのレオナルド…
(69)体のことしか考えられない
<智恵のない生き方はむなしい>
先月は日本中がオリンピック一色でした。同じ試合、同じ場面が、いくつものチャンネルで、何度も何度も朝から晩まで放映されることもしばしばでした。「○○さんが金… (70)『知っているつもり』の苦しみ
<エゴと煩悩のメカニズム>
『知る機能』がこころですと仏教は定義しています。しかし「私はこころで何でも知っている」と思うようになったら、これは問題であると思います。仏教は、こころは正しく、…
(71) 社会が認めるのはどのような人か
<道徳が支える人生に後悔なし>
人はどのように生きていればよいでしょうか。何か理想的な生き方というものでもあるのでしょうか。自分にぴったりと合う特別な生き方があるのでしょうか。間違った… (72) 自分しか愛せない
<智恵のある人は自分を守る>
私たちは誰のことが一番好きでしょうか。誰のことを真剣に心配したり、気にしたりするのでしょうか。子供のこと、両親のことなどが思い浮かぶかもしれませんが、実は…
(73)守る気になれない道徳
<説得力を持たない道徳は無意味です>
「悪いことはしてはいけません」「嘘をついてはいけません」「人をだましてはいけません」「怠けてはいけません」「他人のものを盗ってはいけません」…このような… (74)何に頼れば安全ですか
<不安がこころの自由を壊す>
宗教というのは、何かを信仰して、それに頼って生きることだと言ってもそれほど間違いはないと思います。完全な自信を持って生きている人はほとんどないでしょう…
(75)仏陀の出現は幸福です
<祝福を行うWesak祭り>
5月7日の満月の日に、仏暦は2545年に変わります。テーラワーダ仏教徒にとって、この日は365日の中で一番大切な日です。この日1日、ほとんどの人々は修行に… (76)なぜ私は不幸になるのでしょう
<不幸の原因は自分のこころの中にある>
私が不幸なのはなぜでしょうか。色々と努力しても、物事がうまくいかないのはなぜでしょうか。真剣に真面目にがんばっているのに、なかなか希望通りの結果には…
(77)仇敵のすみかは自己のこころの中
<知らず知らず自己破壊へ歩む人>
仏典に、マールワーという名前の蔓の話があります。種が大変小さく、風で飛んで、他の木の幹に粘着し、その木に寄生して成長します。木にマールワーの種が… (78)なぜ生命は不幸を目指すのか>
<悪は善を装ってでも人を襲う>
楽しくて、やらずにおれない行為の危険性について考えてみましょう。我々が生まれつき、また本能的に、実行すれば楽しくなるような行為は、限定されているような気が、…
(79)本物と勘違い
<真実の道は地道に歩むもの>
風船、金銀モールなどの飾りは、他の何よりも先に目に入ります。派手に自分を演出していますが、実は何の価値もない、すぐゴミになるものです。金紙銀紙と違って… (80)無駄な責任転嫁
<すべては自分の責任であった>
自己責任について、初期仏教の立場がどのようなものかについて、考えてみましょう。他人に対して責任を持ちなさいと戒めるのは簡単なことです。言う側にとっては、…
(81)他人の為は『他人の為』か
<災難は『主義』が起こす>
「他人の救いの為に努力する」ということは、ほとんどの宗教で尊い道徳だと思われています。皆のために頑張る、皆を幸せにしてあげる、世界を、人類を救済してあげる… (82) どう生きればいいの?
<曖昧に生きることを避けるための4原則>
私たちは、どのように生きていけばよいのでしょうか。誰でも気軽に訊く質問ですが、簡単に答えるのは難しいと思います。この気軽な質問にお釈迦さまが示した一つの…
(83)論より正悟
<仏法は思考のゲームではありません>
「立ち上がれ、努力せよ、怠るなかれ」というお釈迦さまの言葉があります。お釈迦さまは当時の他の宗教家たちや観念的な理想ばかり語る夢想家たちと違い、目的に達… (84)この世は泡沫です
<「ある」という苦と「ない」という苦>
「ものがある」と思うと、無限の苦しみが心に流れ込むのです。では、「ものがな



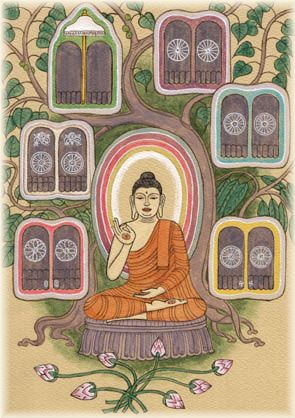

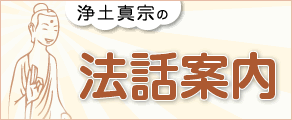
コメント