日本の仏教は、聖(ひじり)によって支えられた
中世日本の墓は村落墓地が主体でした。
その村落墓地へ、通りがかりの旅のお坊さんを呼び止め、「生活の面倒はみるから、このお堂を守ってもらえないか」と頼んだのが、住職という職業の始まりといわれます。
異国と接していないものの、隣接する地域と山や海で隔てられたこの国では、旅人=哲学者であり、旅をする僧侶(聖)は人生の達人でありました。
しかし、1つの寺を住職一家が支えるというこの風習は、複数の僧侶がサンガを形成して寺を守る海外の仏教とくらべ、僧侶の堕落も招きました。聖(ひじり)はいまでも存在する!
墓じまいによって、たとえば金銭の話しかしてくれないような堕落した僧侶との縁を切り、新たな弔い先を見つけようとする場合、慕えるお坊さん(=聖)を見つけてほしい。
そういった思いのもと、寺と墓をめぐる社会的背景と死後事務などの法的手続きについてまとめた『聖の社会学』(2017、イースト新書)をこのたび上梓しました。
墓じまいをご検討中のかたをはじめ、宗教法人関係の案件を受けていらっしゃる士業の先生がたにも一読いただければと思い紹介させていただきました。
聖の社会学 (イースト新書) 新書 – 2017/4/9 勝 桂子
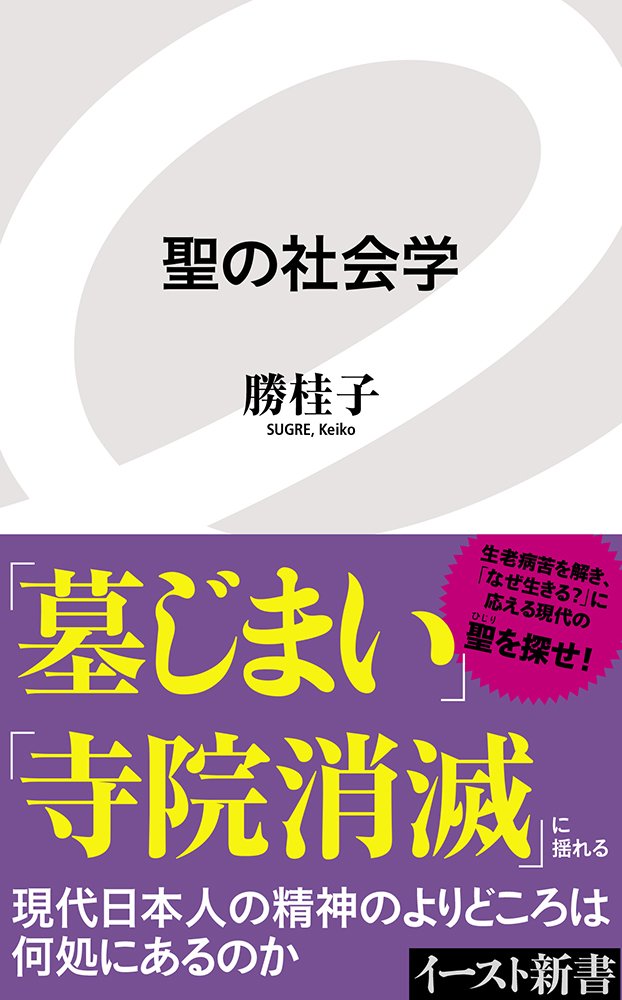



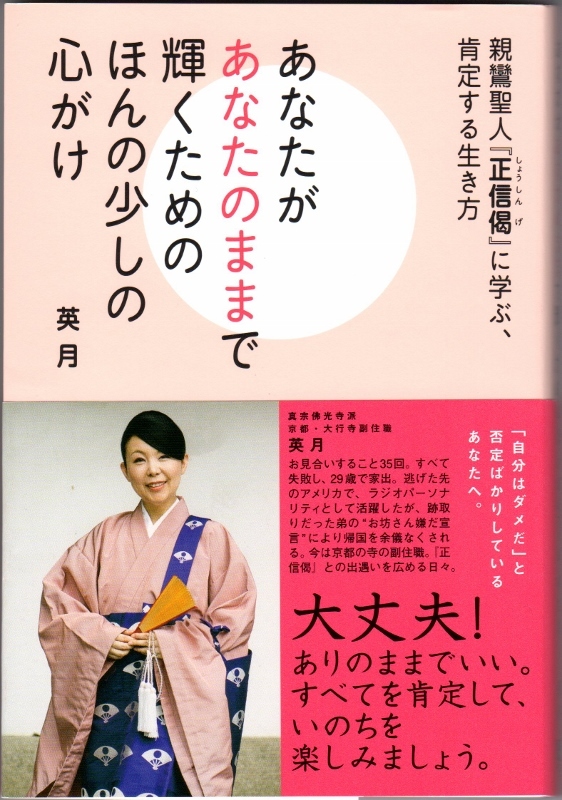
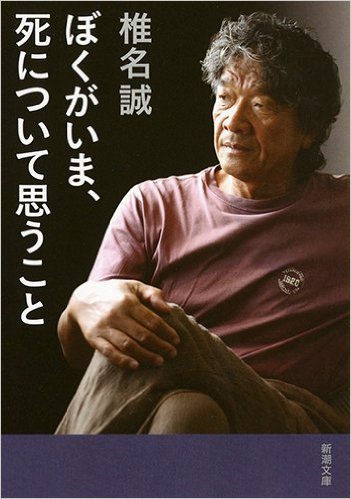

コメント