大阪市東住吉区・真宗大谷派恩楽寺衆徒の乙部大信さん(36)は、3年前から自坊を会場に葬儀を営む「お寺葬」を始めた。
「葬儀社の会館で行う葬儀と比べて遺族との距離が近くなり、法話も聞いてもらいやすい」と手応えを感じている。
「聞法」を重視する浄土真宗ではあらゆる仏事で法話をするが、従来の葬儀社主導の葬儀では思い通りに法話ができないことが少なくない。法話のさなかに葬儀社の社員から「ご遺族がお疲れですので……」と制止されることもある。
「仏法を押し売ることに貪欲で傲慢な私」と笑う乙部さん。「従来の葬儀が物足りないようになった」のが「お寺葬」を始めた大きなきっかけだが、寺の行事にあまり参加しない門徒に働き掛けることで恩楽寺への所属意識を高めてもらうと同時に、門徒以外の会葬者にも寺の存在を浸透させる狙いもある。
「お寺葬」では臨終時に「必ず一番最初に恩楽寺に連絡」してもらうことから遺体搬送や湯灌、納棺、火葬など全てのプロセスに関わる。葬儀前日に営む本堂での通夜法要後は寺の座敷にお斎会場を設置し、食事を共にしたり、布団を用意したりすることもある。
既存の施設や寺が常備する祭壇を使用し、寺族も様々な手伝いをするため、遺族にとっては葬儀費用が比較的安価になるのがメリットだが、乙部さんは「葬儀社の協力も不可欠。きちんともうけが出るよう配慮して良好な関係を築く必要もある」と言う。
また「例えば、遺影の準備を喪主以外の親族に任せるなど何かの役割を与えることも大切。喪主の負担軽減だけでなく、葬儀に対する当事者意識を持ってもらえる」と説明。「すると儀式や法話への共感が高まり、仏教やお寺に関心を持ってもらえる。『お寺葬』の後、報恩講など寺の行事にお参りに来てくれる人が増えた」と喜ぶ。
これまでに2度、門徒対象の「お寺葬」の説明会を開いたが、7月7日に初めて地元の大阪教区の僧侶を対象にした説明会を開催し、十数人の参加者に惜しげもなくノウハウを公開した。
乙部さんは「最初は他の寺院に内緒にして自坊だけでやる方が得だと思っていた」。しかし「閉塞しつつある寺院の運営状況は仏教界全体の問題。自坊だけで盛り上がるのではなく、ご門徒や他寺院、宗門全体が元気にならないと共倒れになる。共に学ぶ仲間が最も大切だ」と力を込めた。






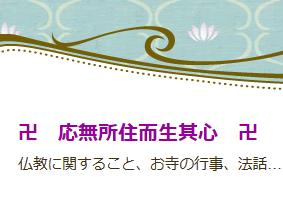
コメント